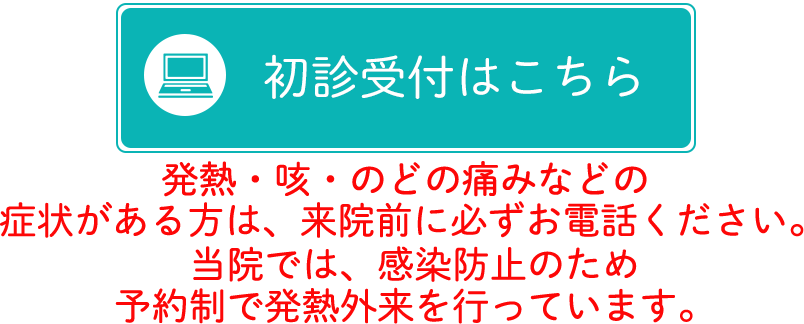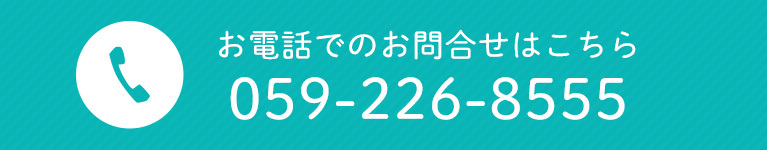診療のご案内
診療方針
当院は、患者様とのコミュニケーションを大切にし、患者様が抱える症状や不安に真摯に向き合います。お一人お一人の健康状態を把握し、患者様に合わせた治療計画を立案し、健康な日常生活を取り戻せるようサポートいたします。
生活習慣病

生活習慣病ってどんな病気なの?
身体によくない生活習慣の影響により、発症してしまう病気のことです。
当院ではこのような生活習慣病の代表例である「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」の治療を積極的に進めています。また、尿酸値が高い方や、睡眠時無呼吸症候群に悩んでいる方、また「現在はまだ生活習慣病にはいたっていないが、肥満で悩んでいる」という方は、当院を受診して下さい。
高血圧症

高血圧症とは、血圧が正常値よりも高い状態にあることをいいます。
高血圧症は多くの場合、自覚症状がほとんどないままに進みます。しかし放置しておくと、血液が流れにくくなります。血液はさまざまな細胞に酸素や栄養素を送り込む役目を担っていますが、高血圧症になるとこれがうまくいかなくなり、多くの合併症を引き起こすようになります。
高血圧は、ときに心筋梗塞や脳卒中のような命に関わる疾患を招きます。そのため、早急に130/80mmHg未満の状態になるように血圧をコントロールしていくことが求められます。運動不足や塩分の摂りすぎは高血圧症のリスク要因となるため、まずはこれを避けましょう。また、必要に応じて投薬治療を受ける必要があります。
糖尿病

私たちが摂取した食べ物は、「ブドウ糖」となって体を動かすエネルギーとして使われます。
そしてこの糖の代謝に関わるものとして、「インスリン」があります。インスリンはブドウ糖をエネルギー源として細胞に取り込む役割を果たすとともに、ブドウ糖が血中に残りすぎないように調整するホルモンでもあります。
しかし、摂取する食べ物の量が多すぎたり、インスリンの分泌が悪かったり、インスリンの力が弱かったりすると、糖が体内に残ることになります。この残った糖は心臓病や腎不全、四肢の切断などにも繋がるものです。そのため、糖尿病もまた、早期の発見と治療が必要です。
※糖尿病に関しては、生活習慣以外が要因となることもあります。
脂質異常症

脂質異常症とは、中性脂肪やコレステロールなどの脂質代謝に異常が出ている状態をいいます。
脂質異常症状態が続くと、血管の中に余分な脂がへばりつきます。このへばりついた脂は、血液の流れを阻害し、細胞に栄養と酸素がいきわたることを邪魔します。その結果、心臓や脳などに関わる重い病気をもたらす可能性があります。また、脂質異常症の人は、腎臓病も非常に患いやすくなります。
脂質異常症は、いわゆる「グルメな生活」+「運動不足」によってもたらされることが多いといえます。そのため、脂質異常症もほかの生活習慣病と同じく、日ごろの生活スタイルの見直しが重要です。
胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)
胃のみの検査を行うものだとイメージされている方が多いと思いますが、正確には「上部消化管内視鏡検査」といい、検査の対象臓器は上部消化管(食道・胃・十二指腸)すべてを含みます。
カメラを口から(経口)または鼻から(経鼻)入れて、直接上部消化管の中を観察することや、病気が疑われる部分の組織を採取し病理検査に提出すること(生検)などを行って、病気の診断や評価するということを目的とした検査です。
予約・検査のながれ
①内視鏡検査をご希望の方はご来院いただき事前予約をお願いします
・内視鏡検査前に患者さんの状況、状態を把握するために診察が必要となり、その際に、持病や服薬中の薬等を同意書を用いご質問させていただきます。
②検査の前日の午後9時から絶食をお願いします。
・夕食は固いものを避け、消化の良いものを午後9時までに食べてください。
・水分は、適度な水やお茶以外は控えてください。
③検査の当日は服装、朝食、飲み物にご注意を
・服装はリラックスして検査が受けられるような格好でお願いします。
・朝食は食べないでください。
・来院時間は事前説明した際にお伝えした時間にお越しください。
・朝の薬は、検査後に内服してください。
④検査時間は10分程になりますが、状況によっては、時間がかかる場合があります
⑤検査終了後に結果のご説明をします
⑥検査後の注意
・飲食は、喉麻酔が効いているため検査後1時間くらい経ってから、取るようにしてください。
・検査後は院内でしばらくお休み頂いてから、ご帰宅して頂くようにしております。
ヘリコバクター・ピロリ菌
ヘリコバクター・ピロリ菌は胃粘膜に生息しています。
胃粘膜は、強力な酸である胃酸に覆われているため、従来は、細菌も存在できないと考えられていました。しかし、最近の研究により、胃の中でも存在できる、ピロリ菌という細菌がいることがわかりました。
ピロリ菌は、ウレアーゼという酵素を出して、自分の周りにアルカリ性のアンモニアを作り出すことで、胃酸を中和しながら、胃の中に存在しています。
ピロリ菌の感染経路は不明ですが、飲み水や食べ物を介して口から菌が入ってしまうことで感染すると考えられています。さらに、免疫機能が十分ではない幼児期に感染する可能性が高く、免疫機能が確立している成人が新たに感染する可能性は低いようです。
日本人の場合、年齢が高い方ほどピロリ菌に感染している率が高く、60歳代以上の方の60%以上が感染しているといわれています。
これは、水道水などのインフラがまだ整っていなかった時期に幼少期を過ごしたためではないかとされています。実際、衛生環境が整った頃に生まれた若い人たちの場合、感染率が低くなっています。
また、ピロリ菌に感染しているだけでは、症状などは出ませんが、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎の患者さんはピロリ菌に感染している方が多く、ピロリ菌が胃や十二指腸の炎症やがんの発生に関わっていると考えられています。
ピロリ菌を除菌すると、胃や十二指腸の病気になったり、これらの病気が再発しにくくなることから、現在では、感染しているかどうかを高い精度で診断する検査方法が、普及しています。もし、ピロリ菌に感染していることが分かった場合は、積極的に除菌することが推奨されています。
診断・検査
ウレアーゼ試験:ピロリ菌のもつウレアーゼ活性を測定し、菌の有無を診断します。
組織鏡検法:内視鏡で胃粘膜を採取し、染色し、顕微鏡で菌の有無を診断します。
培養法:内視鏡で胃粘膜を採取し、それを培養し、菌の有無を診断します。除菌が成功か否かを判断するときに使われています。
抗体測定:血清および尿中のピロリ菌の抗体を測定します。
尿素呼気試験:検査試薬を飲み、吐き出した息の中の炭酸ガスを測定し、ウレアーゼ活性を測定し菌の有無を診断します。
便中抗原測定:便の中のピロリ菌抗原を測定します。
除菌方法
ピロリ菌のいる患者さんには、胃酸分泌を抑える薬と2種類の抗菌薬を用いる除菌療法があります。この方法の除菌率は約90%です。
一度除菌されると、再発の可能性は2~3%と考えられています。服用時に抗生物質による、下痢・軟便などの副作用が現れることがあります。
大腸カメラ(下部消化管内視鏡検査)
内視鏡を肛門から挿入し、肛門、大腸、小腸の一部(回腸末端)に異常がないかどうかを調べる検査です。小さなポリープが見つかった場合はその場で切除可能です。一定以上の大きさがあるポリープやその他の病変は一部組織を採取し病理検査に提出し、その結果から今後の診療計画を立てます。
大腸内には便が存在しており、そのままでは観察したい大腸粘膜部分が隠れてしまい検査に時間がかかったり、正確な診断が受けられなかったり、ということになりかねません。そのため、検査を受ける前日から大腸内を綺麗にするための準備が始まります。
予約・検査のながれ
①内視鏡検査をご希望の方はご来院いただき事前予約をお願いします
・内視鏡検査前に患者さんの状況、状態を把握するために診察が必要となります。
・その際に、持病や服薬中の薬等ご質問させていただきます。
※抗凝固剤など(血液をサラサラにするお薬)を使用されている方は休薬指示がでることがあるため医師看護師に必ずお伝えください。
②検査の前日の午後9時から絶食をお願いします
・夕食は固いものを避け、消化の良いものを午後9時までに食べてください。
・前日のお食事は大腸内視鏡専用検査食の用意もあります。
・水分は、適度な水やお茶以外は控えてください。
・状態により夕食後に緩下剤を服用して頂くことがあります。
③検査当日は、朝食、飲み薬にご注意を
・朝食と昼食は食べないでください。
・常用薬については、事前確認うえ問題ないものを内服していただきます。
・検査の約2時間前から腸管洗浄液を数回に分けて2Lほど服用していただきます。
・当日は、検査着に着替えて頂きます。
④検査時間は20分前後
・大腸カメラは患者さんの腸管の状態により、検査時間や挿入時の苦痛に個人差があります。
⑤検査後の注意
※検査中に小さなポリープが発見した場合その場で切除することができますが、状況により切除はできません。
健康診断
令和7年度 津市特定健康診査・特定保健指導
| 実施期間 | 個別健康診査:令和7年7月から令和7年11月30日まで 集団健康診査:令和7年8月から令和8年1月25日まで | |
| 対象者 | 津市国民健康保険に加入の40歳から74歳の人(昭和25年9月1日から昭和61年3月31日生まれの人) 注:妊産婦や長期入院、施設に入所している人は特定健康診査の対象とはなりません。 注:昭和25年9月1日から昭和26年1月25日生まれの人は、75歳の誕生日前日までに特定健康診査を受けてください。 | |
| 受診料(自己負担額) | 和6年度市民税・県民税課税世帯…500円、令和6年度市民税・県民税非課税世帯…無料 | |
| 内容 健診予約方法 | 身体計測、理学的検査、血圧測定、血液検査(脂質・肝機能・糖代謝・尿酸・腎機能)、貧血検査、心電図検査、検尿を行い、一定の基準のもと医師の判断により、眼底検査を行います。 結果を通知する際に受診者全員に、自らの健康状態を認識し、健康的な生活習慣への理解を深めるために必要な情報を提供します。 健診予約は、直接電話で予約をお願いします。 |
令和7年度 津市がん検診・健康診査(39歳以下)・健康増進法健康診査
| 実施期間 | 令和7年7月から令和8年3月まで | |
| 対象者 | 津市に住民登録があり、職場等で検診を受ける機会がなく、自覚症状のない人 | |
| 受診方法 | がん検診等を受診するには、受診券が必要です。 次に該当する人には6月下旬に受診券を送付予定です。 ・30歳、35歳の女性 ・40~45歳、50歳、55歳、60歳の人 ・40~69歳の津市国民健康保険加入者 (上記対象者の年齢基準日は令和8年3月31日時点) ・過去3年間に津市が実施したがん検診等を受診した人 | |
| 受診券の申請方法と受付開始日 健診予約方法 | 詳しくはこちら 健診予約は、直接電話で予約をお願いします。 |
津市後期高齢者健康診査
| 実施期間 | 令和7年7月から11月まで。 | |
| 対象者 | 後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の方。 | |
| 受診料(自己負担額) | 無料 | |
| 内容 健診予約方法 その他 | 基本的な健診項目(問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、胸部X線検査など)と、医師が必要と認めた場合の詳細な健診項目があります。 健診予約は、直接電話で予約をお願いします。 受診券は6月下旬に郵送されます。 がん検診等を同時に受診する場合は、後期高齢者健診の申し込み時にお申し出ください。 詳しくは、広報津7月1日号または保健センターへお問い合わせください。 |
予防接種
ワクチン接種費用(税込み)
※項目をクリックで詳細が確認できます。
| 生水痘ワクチン | 7,900円 |
|---|---|
| おたふく風邪ワクチン | 5,900円 |
| MRワクチン(麻しん風しん混合) | 8,900円 |
| 肺炎球菌ワクチン | 8,400円 |
| (対象者) | 2,600円 |
| (対象外・申請者) | 4,000円 |
| インフルエンザワクチン | 3,900円 |
| インフルエンザワクチン(フルミスト 2歳以上19歳未満) | 8,000円 |
| B型肝炎ワクチン | 6,600円 |
| 日本脳炎ワクチン | 5,500円 |
| 二種混合ワクチン(DT) | 3,300円 |
| 破傷風ワクチン(トキソイド) | 3,500円 |
| RSウイルスワクチン(アレックスビー) | 25,000円 |
| 新型コロナワクチン(一般) | 15,300円 |
| 新型コロナワクチン(津市高齢者) | 4,600円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 20,000円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス*定期接種 津市在住対象者) | 6,600円/回 |
| 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン) | 7,900円 |
| 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン*定期接種 津市在住対象者) | 2,600円 |
*定期接種はお住まいの(住民票のある)市町村(特別区を含む)で実施されます。
費用については、各市町村で異なりますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。
自由診療
AGA治療(男性ホルモン型脱毛症)

AGA治療(男性ホルモン型脱毛症)は、可能な限り早期から行うことが重要です。早期治療により、症状の進行を遅らせ、治療期間と費用を節約することができます。
当院ではジェネリック医薬品の利用も可能ですので、お気軽にご相談下さい。
※ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間が終了した後に開発される後発医薬品です。先発医薬品と比べて安価ながら、効果はほぼ同等です。
AGA治療の副作用
AGA治療の副作用には、男性機能低下や肝機能障害、頭皮トラブルなどが挙げられますが、使用する治療薬によって症状が異なります。もともと肝臓が弱い人やアレルギー体質の人は、治療薬が体に合わないこともあります。
ED治療(勃起不全・勃起障害)
ED治療薬は、血管を拡張することで血流を改善し、勃起しやすくする薬です。強制的に勃起させたり、性欲を高める作用は無いため、勃起が収まらないという心配はありません。
勃起効果が長時間持続する治療薬を服用する場合も、性的興奮なしで勝手に勃起してしまうということはないので、安心してください。
以下の患者様には、処方出来ない事が有りますのでご了承下さい。
ED治療薬の副作用は主に以下が挙げられます。
鼻づまり、顔のほてり、消化不良、目の充血、頭痛
硝酸薬を使用している方、ED治療薬にてアレルギーを起こした方、心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる、心筋梗塞(6か月以内)、低血圧(90/50mmHg以下)、高血圧(170/100mmHg以上)、脳梗塞・脳出血(6か月以内)、重度の肝障害(肝硬変)、網膜色素変性症(進行性の夜盲)
服用中のお薬がある場合は、必ず『お薬手帳』などお薬の名前がわかるものを持参ください。
※ED治療に係る全ての診療費は、健康保険の対象となりませんのでご了承ください。
歯科
歯科の疾患と全身疾患には密接な関係があることがわかってきており、その繋がりが一般的にも認識されはじめてきました。
睡眠時の無呼吸検査、誤嚥(ごえん)性肺炎の予防、糖尿病や高血圧などの全身疾患の予防など、歯科と内科が連携して患者様一人ひとりのお口の状態や体調、お身体にあわせた治療プランをご提案しています。
「ちゃんと睡眠を取っているのに日々の疲れが取れない」、「糖尿病が歯周病治療で改善すると聞いたけど、どういうこと?」といった疑問やご相談がありましたら、しっかり説明させていただき、併設の歯科と連携させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
その他
睡眠時無呼吸
睡眠時無呼吸症候群は眠り出すと呼吸が止まってしまう病気です。呼吸が止まると血液中の酸素濃度が低下するため、目が覚めて再び呼吸し始めますが、眠り出すとまた止まってしまいます。
これを一晩中繰り返すため、深い睡眠がまったくとれなくなり、日中に強い眠気が出現します。酸素濃度が下がるため、これを補うために心臓の働きが強まり、高血圧となります。酸素濃度の低下により動脈硬化も進み、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなります。さらに睡眠不足によるストレスにより、血糖値やコレステロール値が高くなり、さまざまな生活習慣病やメタボリック・シンドロームがひきおこされます。
1時間あたり10秒以上の呼吸停止が20回以上出現するような中等症・重症の睡眠時無呼吸症候群を放置すると、心筋梗塞・脳梗塞・生活習慣病・眠気による事故などを引き起こし、死亡率が非常に高くなるため、すぐに治療が必要です。
呼吸機能検査
呼吸機能検査では、息切れする、呼吸が苦しい、咳が出る、痰が出るなど、肺の病気が考えられる時に、肺の容積や空気を出し入れする換気機能の強さを測定し、呼吸機能に異常がないかを調べます。検査の結果により、肺の病気の診断、重症度・治療効果などの確認を行います。
尿素呼気試験
尿素呼気試験は、胃炎や消化性潰瘍の原因菌として考えられているピロリ菌の診断及び除菌治療効果の判定を目的としています。
腹部エコー(腹部超音波検査)
超音波検査は、超音波を用いて、内臓から返ってくる反射波を画像化して診断する検査です。仰向けに寝て頂き、腹部にゼリーを塗って検査をします。
対象とする臓器は、肝臓、胆のう、胆管、膵臓、腎臓、脾臓。
消化管ガスの影響や体型によって、抽出が難しい事がありますので、抽出範囲での評価となります。各臓器の腫瘍をはじめとして、結石、脂肪肝等の生活習慣病と関連が強い所見も発見できます。
頸部エコー
頸動脈をエコーで観察して頸動脈の詰まり(プラークや血栓)や狭窄の有無から動脈硬化の進み具合を観察します。脳梗塞、狭心症、心筋梗塞など全身の動脈硬化疾患の発生リスクを早期発見します。